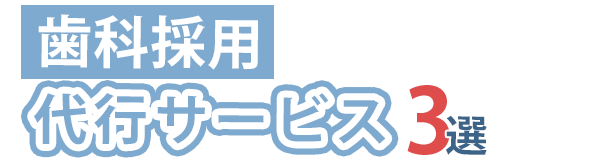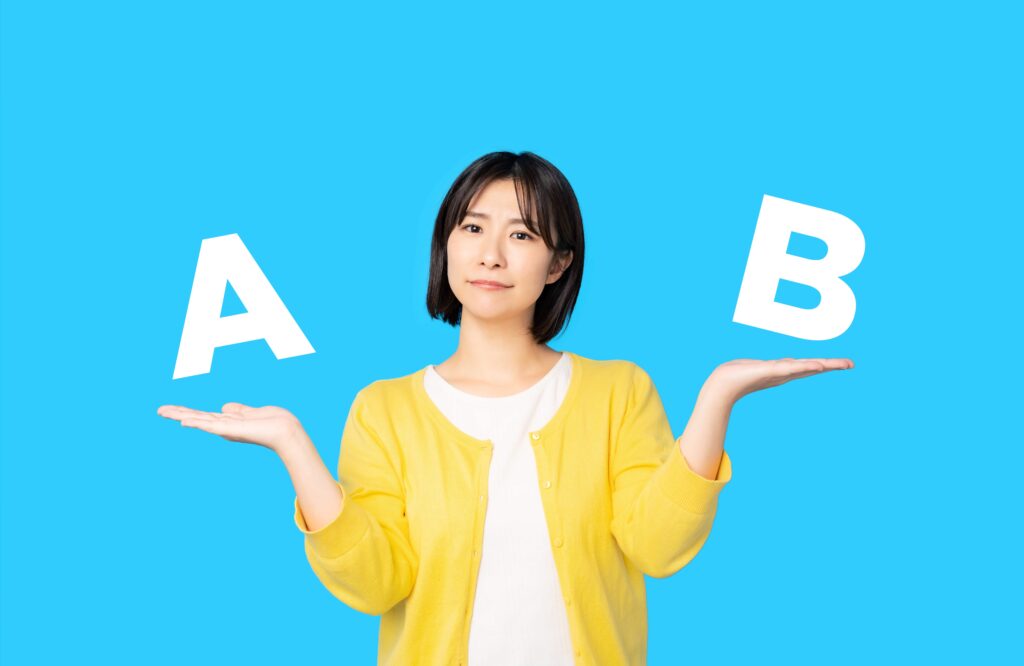歯科衛生士の求人を出しても応募がこない歯科医が多くなっています。高齢化で需要が増える一方、養成校の定員不足と待遇格差が離職を招き、人材が不足しているためです。今回は、採用が難しい最大の理由と解決策を、実例を交えてご紹介します。採用媒体の選び方や面接の組み立ても紹介するので、人手不足を逆転するヒントにしてください。
歯科衛生士の需要は年々高まっている
厚生労働省の医療施設動態調査では、訪問診療を届け出る歯科診療所が2013年から2023年で約2倍に増えました。高齢者が増え、在宅口腔ケアの需要が拡大したことで、外来だけでなく自宅や施設でも歯科衛生士が欠かせません。一方、養成校の定員はほとんど増えず、新卒の人数は伸び悩んでいます。口腔機能管理料の新設や40歳・50歳・60歳での検診義務化方針などの政策も予防中心の診療を後押しし、衛生士が担当するメインテナンスやインプラント管理の範囲を押し広げています。
こうした背景から、求人倍率は2022年度で5倍を超え、都市部では給与競争が激化し、地方では応募が集まらない状況が続いています。需要の伸びに供給が追いつかないまま進めば、2030年には衛生士が約2割不足するとの推計もあり、医院間の採用競争はさらに厳しさを増すと予想されます。
歯科衛生士の募集が難しい理由
歯科衛生士の募集が難しくなっていることには、複数の理由が重なっています。まず、歯科衛生士の数が足りていないことが挙げられます。予防歯科や訪問診療が広がり、衛生士の仕事は年々増えています。
しかし、養成校の定員はほとんど増えていないのが現状です。そのため、新しく資格を取る人は毎年約7,000人にとどまっており、需要に対して供給が追いついていないのです。
次に挙げられるのは、衛生士が職場を選ぶときに重視するポイントが変わってきていることです。以前は給与や休日が注目されていましたが、今は担当制でしっかり患者を診られるか、教育制度があるか、最新の機器が使えるかなど、スキルアップや働きやすさがより重視されています。
こうした要素を備えていない医院には応募が集まりにくく、とくに待遇や制度の整備が遅れている地方の医院では人材の確保が難しくなっています。
そして、職場環境が原因で辞める人が多いことも理由のひとつです。スタッフの人数が少ないと業務の負担が重くなり、残業や休日出勤が増えることで働きにくさを感じるようになります。
その結果、早期に退職してしまう人が多くなり、さらに人手不足が進むという悪循環が起こります。また、退職が続くと職場の雰囲気も悪くなり、それが口コミなどを通じて広まることで応募者から敬遠されてしまいます。
このように、歯科衛生士の募集が難しい背景には、人材の供給不足、働く人の意識の変化、労働環境の問題といった複数の要因が関係しています。
歯科衛生士の人材募集が難しい最大の原因は「差別化不足」
歯科衛生士の人材募集が難しい最大の原因は、他院との差別化ができていないことです。応募者が求人を見て応募を決めるとき、給与や休日だけでなく、その医院でどのような経験が積めるか、どんな働き方ができるかといった点を重視しています。しかし、多くの医院は求人票でそれを十分に伝えられていません。似たような条件が並んでいることで、応募者の目に留まりにくくなっています。
たとえば、スタッフ同士の仲が良い、アットホームな職場という言葉だけでは、ほかの医院とどう違うのかが伝わりません。応募者が知りたいのは、担当制が導入されているか、患者との関係性を築ける環境があるか、どのような機器や治療を扱っているかといった具体的な情報です。
さらに、教育制度が整っているか、キャリアアップが目指せる環境かどうかも重要です。入職後のイメージがもてない医院には、安心して応募できません。
また、見学や面接の場でも差が出ます。在籍中の衛生士が案内役となり、実際の仕事の様子や使っている器具などを説明することで、求職者はリアルな職場の雰囲気を感じ取ることができます。
それに対して、見学の際に衛生士と話す機会がなかったり、業務内容の説明が不十分だったりすると、応募を見送る判断につながります。さらに、公式サイトやSNSなどで情報を発信していない医院は、働くイメージをもたれにくく、応募数の面でも不利になります。
今は情報収集の手段が多様化しており、求職者は複数の媒体を見て比較しています。だからこそ、求人票や公式サイト、面接の場など、あらゆる接点で他院との差をわかりやすく伝える工夫が必要です。
差別化ができていないことは、募集においてもっとも大きな障壁となっており、これを解消することが採用成功への第一歩です。